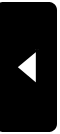思考停止という思考がもたらす戦争想念とは。その人たちには何ら悪気はない。平和主義で、穏健派。にも拘わらず闇波動に寄与してしまうメカニズムとは
高貴なるライトワーカー、光の戦士がた、いかがお過ごしでしょうか。
先日もまた、かなり大きな地震が起きましたね。今年に入ってから、各地で起きている地震の頻度が、これまでにないほどの数に上っているそうです。
一般的には恐ろしい厄災の前兆とされるこれらの地震ですが、スピリチュアル的にはむしろ逆だというお話しをしました。
頻発している地震も、来年起きる恐れのある/あった「壮絶な事態」を回避するために、つまり大難を小難に変えている事象の一つだと考えられます。それが、「恐れがある」なのか、「あった」なのか──現在形か過去形かは──、まさに私たちがどこまで未来を変えられるかにかかっています。
光の人たちは、すでに過去形となったタイムラインの方に乗っていると思いますが、そうでないタイムラインを行く人たちの負の牽引力もすごいので、まだ完全に安定的とは言えないでしょう。ぬかりなく実践を続ける必要があります。
現会長が、「大難を小難に」と盛んにおっしゃるんですが、実際のところ、彼女には、とんでもないものが見えているんだと思います。口には出しませんけど。(出すとしても、かなり言葉を選んでいます。)
私はというと、波動それ自体の様相を見ています。夢とか半醒半睡の際にビジョンで見る場合もありますが、それも現状の波動の様相を象徴化したものです。
最近では、ものすごく綺麗な水の流れを夢で見たかと思えば、恐ろしい怪物──五、六十メートルはありそうな巨大なワニとか──を見たりです。めまぐるしい感じですね。
じゃあその怪物の正体は何かというと、人々のネガティブな想念波動が集まってできたもの、つまり線形波動/暗黒波動の象徴なのです。想念波動の世界では、光の潮流が勢いを増す一方で、闇波動も浮き上がってきているということでしょう。
かつてよく見ていたのは道です。自分の乗っているタイムラインが、現状のまま行くとどうなるかという意味で、わかりやすいビジョンです。まっすぐで舗装された道路であったり、また、その先が上に向かっているときもあります。かと思えばクネクネと紆余曲折する道であったり、背の高さほどもあるボウボウの雑草に覆われて先が見えなかったり、木々の生い茂る森の中を分け入っていく、道なき道になったりもします。
実は醍醐味はここからです。困難な道を見ている最中でも、祈り、マントラを唱え、マカバ瞑想をしますと、その場でビジョンが変わり、雑草が除かれ、くねった道はまっすぐになり、道が開けてきたりします。祈った瞬間に未来が変わってしまうのです。
「三大ツール」をはじめとする神聖なるツールの威力の凄さが、わかろうというものです。瞬時に未来を変えてしまえるわけですから、未来の上方修正ツールとも言えますね。もちろんビジョンを見るときだけそうなっているわけでなく、見えようが見えまいが、化学反応のようにそうなります。
つまり光の皆様は、実践をすることで、常日頃から未来の修正をしているわけです。実践をすればするほど、実践する方が多いほど、未来は上方修正されます。繰り返すうち、今は乱高下しているタイムラインが、徐々に上方に昇る方向に安定してきます。
預言や予知に関心を抱くスピリチュアリストは多くても、その未来予知に一喜一憂するだけの段階の人にはわかりえない、「未来をその場で変える」ことを、ツールの威力が鮮やかに成し遂げます。
言い換えるなら、ツールの威力を理解し実践できることが、とりもなおさず、その人が本当の意味で光の戦士である証左ということでしょう。

理解の深度がツールを活性化させる
さて、ではレクチャーの続きですが、
前回は、「攻略マントラ」の意義について申しました。今回はその続きで、戦争想念を掘り下げてみたいと思います。
これまで提供してきた攻略マントラは、「戦争想念波動の戻し」「戦争タイムラインからの乖離」「U・P氏からのネガティブ想念の戻し」といったもので、ほぼ戦争や独裁者など、世界を最も不穏な状態に陥らせるネガティブからの脱却を図るものです。つまり、戦争想念の攻略が、何はともあれ優先順位的に先、ということです。
ここでいう優先順位は、重要度の高い低いではなく、レクチャーの順序として先に解説したい、という意味です。来年に向けて、可能な限り過酷な道を回避したいためです。
一連の解説のあと、これまでの攻略マントラに追加して、独裁者からの想念波動の戻しのマントラを提供するつもりです。
そのマントラも含め、今回のレクチャーを通して、マントラの意義をよく理解したうえで唱えることで、効果が格段に上がると思われます。
以前から申しておりますが、この、理解の深度がツールを活性化するということ、そのための考察であること、あらためてご認識いただければと存じます。

戦争想念について、あらためて考察してみる
今回のR国によるU国への侵略戦争を通して、私は、戦争想念というものについて随分と考えさせられました。
私は以前見た、とある番組を思い出しました。第二次大戦当時の、ナチス・ドイツの指導者H氏に関するものです。ナチスについて考察する番組は、意外と多いのですが、大抵はH氏に対して批判的です。あれだけのことをやらかしたのですから当然ですが・・
ところがその番組に出ていた人たちは、H氏のシンパなのか、擁護する発言をしていました。いわく、「Hは戦争を好まなかった」「戦争をしたくはなかったのに、イギリスが和平を拒否したから、戦わざるを得なくなった」といった調子です。
実際、H氏が、戦争を特に好んでする人物ではなかったのは、私も同意です。
確かに彼は、戦争そのものを望んでいたわけではないのです。事実彼は、電撃戦などと称して、ベルギーやフランスなど他国への侵略を、ものすごいスピードでやってのけました。さっさとケリをつけたかったのです。この点、戦争そのもので利益を得ようとするタイプの人だったら、もっと戦いを長引かせたでしょう。戦争はH氏にとって、自分に従わない場合には容赦しない、という戦いにすぎません。
彼が望んでいたのは、世界が自分にひれ伏して、服従することです。
自分が人々に何をしようと──支配しようと、財産を没収しようと、自由意思や主権を無視しようと、言論弾圧しようと、ユダヤ人や障がい者を虐待しようと、何をしようと──、人々が自分を崇拝し、一切逆らわずに思い通りに動いてくれれば、別に戦う必要はありませんからね。
もちろん戦争そのものを好む人たちもいます。H氏のような独裁者にすり寄って、戦争で利益を得ようとしたり、そもそも戦闘が好きな人もいるかもしれません。戦争を引き起こすプロみたいな人たちです。H氏自身は、それほど軍事に明るくもないし、指揮官としても有能とは言えなかったようです。
ですが、そんなH氏を「彼は戦争を好まなかった」「平和を愛していた」などと評する人々が、今も現実に存在することには驚かされます。
H氏およびナチス・ドイツのいう「平和」とは、人類が彼らにひれ伏し、服従することで成り立つものです。これってそもそも「平和」なんでしょうか?
一方、ドイツの和平の提案を蹴って、戦いを選んだのは当時の首相W・C氏です。
彼は、H氏がこれまでも第一次大戦後の条約やロシアとの条約など、約束事を平気で反故にしてきたのを見ていて、信頼したらとんでもないことになるし、絶対に懐柔されてはならないと考えていました。
ではこの時、WC氏は好戦的で、H氏は平和を望んでいた。イギリスが世界を戦争へと向かわせた、なんて、思いますか?
もしもWC氏がH氏に逆らわず、和平を受け入れていたら・・イギリスだけでなく、世界じゅうの国がH氏に従っていたら・・・世界は、一見、戦争は起きず平穏です。が・・しかし、闇波動に閉ざされた世界となっていたでしょう。
私自身、スピリチュアリストとして、そもそも戦争を好みませんし、戦争は何も生まない、とも思ってきました。でも、もしもこの時、イギリスがドイツの提案を呑んで和平に応じていたら、どうなったかと思うと、やはりWC氏の決断こそが英断であったという思いが、どうしても覆らなかったのです。
実際には、世界中の国が一人の独裁者に従う、なんて事態にはならず、一方ではWC氏が米国も引き込んだ連合国と、一方ではソ連と戦い、ドイツはボロボロになって敗北したわけですが・・・。そうなった原因はドイツが他国を侵略したからです。

暗黒波動は心の中のネガティブな想念と共振して入り込む
ところで、この様子、どこかの国の指導者と似ていませんか? そう、あのP氏です。行動パターンが全く同じなんですよね・・。U国を数日で陥落するつもりで電撃戦を仕掛けたあの遣り口といい、平気で嘘をつくところといい、U国の次は他国に狙いをつけている目論見といい・・。
そして何より、今もって戦争をやめる気を全く見せないところです。
もはや、U国にとってだけでなく、R国自身にとって何の益もない状況です。当初の目論見はもろくも崩れ去り、決して有利とはいえない戦況に陥っています。近隣諸国からのリスペクトも大幅に失いました。経済的にも大きなダメージを受けており、侵攻前の水準には戻れないだろうとも言われています。
しかも、そのようなゆとりのない状況で、他国への侵略の計画がある、という話も聞こえてきています。もう、何かの依存症かと思うレベルで、侵略行為をやめる気がないのです。
あまりに類似しているので、憑依でもされてるのかと思うくらいです。いや、実際にされているかもしれません。
憑依というのは、個々の霊魂だけでなく、想念波動そのものである場合もあります。H氏に憑依されているというより、H氏も暗黒波動に憑依されていたのかもしれません。
暗黒波動は、それ自体が意思を持っていて、人々の心に入り込み、操ります。
憑依は、共振によってなされます。人々の心の中にあるネガティブな感情が、暗黒波動と共振してしまうと、連中はその人の心に入り込むことができます。そして、欲望、執着、対立、差別、憎悪などを増幅させ、世界をより抑圧的で、より支配的な方向へと向かわせます。古来から連綿と活動を続けていて、人心を操っています。
連中にとって、最も操りやすく、そして、操ることで最も大きな効果が出るのが独裁者です。というか、そういうタイプの人間に憑りついて、大きな地位に就くように仕向けているのかもしれません。

一見すると穏健派の人たち
ところで、そんな侵略者たちが引き起こした戦争と、双方の対立によって起きた戦争は、一見すると、戦闘行為をしている点では同じです。
でも先日、例の中東で勃発した戦争について特集した番組を見ていて、その内容もさることながら、R国の侵略戦争と、波動的にも全く違うことに驚かされました。
しかし、戦争を否定する立場から、これらを十把一絡げに戦争で片づける人たちは少なからずいます。
私自身、今回の戦争を通して、認識をあらたにしたので、人のことは言えないのですが・・・。それでも、そうした人たちが、その戦いがなぜ起きているのか、その内実を見ず、とにかく戦っている時点で立場は同じ、と考えるのは、さすがに浅慮だと思ってはきました。
そういう人達の大半は、決して悪気があるわけではなく、むしろ平和主義的な人たちなんですね。
そういえば、上述のWC氏がH氏の和平の提案を突っぱねた際、戦わなければならなかったのは、ドイツ以前に、まずイギリスの議会だったんですよね。あえてことを荒立てずに、穏便に済まそうとする人たちが、WC氏を引き下ろそうとしたようです。
その人たちも、イギリスの安寧を考えてのことだったのでしょうが、やはり浅慮だったと思うのです。H氏やナチスが信用できないことは、それまでの言動から見抜けてもよかったと思いますし、それでいて、ドイツと対立しようとするWC氏を危険視していたのです。
最近では、とある雑誌が、P国とU国の戦いを「ケンカ」と評して物議をかもしました。U国の大使館からも強い抗議を受け、謝罪したそうですが・・・表現の仕方が悪かったような書き方だったので、本当にU国の真意を理解しての謝罪だったかはわかりません。
ネットの声で、「あの雑誌の編集部は、強盗に入られて抵抗していたら、喧嘩はやめて仲直りしましょうとでもいうのか」との批判を見ましたが、まったくその通りだと思いました。
ある主権国家に対し、武力によって領土を奪い、支配することは、主権国家としての尊厳を踏みにじる、あってはならない行為です。
また、これは侵攻当初からあちこちで見かけましたが、R国がU国に侵攻したのには、それなりの理由があった、という、「識者」による「分析」にも、違和感を抱いてきました。その「識者」たちによりますと、双方それぞれ立場や言い分があるんだよ、ということになります。
こういう考えも、一見、知的かつ客観的で、平和主義的にも見えるので、なるほどと納得してしまう人もいそうです。国際間の問題のような、規模の大きなものだと、国際情勢をよく知る専門家でないと、わからないような気持ちになる人もいるでしょう。
でも、こうした問題も、本質的には、個人間で起きる問題と同じです。

国際間の問題も、個人間の問題と本質は同じ
たとえば、学校で、いじめがあったとします。いじめといっても、軽いものから深刻なものまで色々でしょうし、ひとくくりにせず、個々のケースで考える必要があるとは思いますが、近年問題視されている悪質で犯罪的な場合について考えてみます。被害者が教師にそれを訴えた時、中には、両者を仲裁しようとする人がいます。「仲直り」と称して握手させたりですね。
こうした対処の根底にあるのが、「喧嘩両成敗」です。両者、どちらも悪いところがあり、どちらにも相応の言い分がある、という考えです。
これって、ある意味便利な言葉です。それでも、本当に「喧嘩」なら、適切な場合もあるでしょうけど、犯罪的なケースでの、加害者と被害者という構図で、「仲直り」させるのが適切な対処と言えるかどうかです。
もし両者が和解するとしたら、少なくとも謝罪と赦しという構図になると思います。金品の奪取とか、暴力行為による身体的ダメージなどの被害があれば、謝罪だけでは済ませられないケースもあります。少なくとも奪ったものは返す必要があり、暴力行為に関しては、賠償またはそれ以上の刑事的責任が生じる可能性があると思います。
R国によるU国の侵略も、これと同じです。両国間の国際情勢など、むつかしく分析するまでもありません。「U国が侵略されたのには、これこれの背景があった」とか、「R国にも、実はそうせざるをえない事情があった」とか、もっともらしい分析をする人がいますが、武力によって他の主権国家に侵略し、破壊、殺戮、略奪する行為、しかも、最終的に主権をうばって自国のものにしようとする行為に、どんな「事情」があるにせよ、それは犯罪です。ほうっておけば何もかも奪われるのですから、戦わないわけにいきません。
この戦いでも、そろそろ停戦交渉に入ったらどうか、という人がいますが、それならR国が奪った領土をすべて返し、賠償をし、民間人の無差別な殺戮など戦争犯罪については責任を取らなければいけないと思います。少なくともクリミアを含む領土の返還が最低条件だと、U国側が考えるのは当然で、奪われたものを奪われっぱなしで手を打ったら、それはP氏が侵略に成功したことを意味し、和平どころか、独裁者を勢いづかせ、世界をさらに危険な状態に陥らせます。
つまりこれも、ナチス・ドイツと他国との戦争と同じで、侵略する側と防衛する側の戦いです。両者の利害の衝突や確執による戦いとは、そもそも本質的に異なるものです。

思考停止という思考
さて、今回の状況を通して私が学んだのは、戦争想念で最もタチが悪いのは、戦争を引き起こそうとする想念だけではないということです。
ここまで述べてきたように、独裁者やそれに与する者たちが引き起こす侵略戦争は、両者の対立が発展して引き起こされる戦争とは、質を異にするものです。
私が問題だと思うのは、これらの戦争を、区別することなく、「喧嘩両成敗」「どっちもどっち」という言葉で一括りにしてしまう思考です。
そうした人たちは、ご本人は悪意があるわけではなく、平和主義で、穏健派であったり、良心的であったりします。戦争に心をいため、とにかくやめてほしい、みんな仲良くしてほしい、と願っています。
しかしそれが、前者のタイプの戦争にまで当てはめられたら、強盗と、強盗から身を守ろうと戦っている人との間に入って、「仲良くしましょうね」と仲裁するようなものです。
この仲裁によって、何が起きるでしょう。強盗は、自分の奪ったものはそのまま自分のものになり、相手を傷つけた行為を不問に付されます。被害者はそれを取り返したいのに止められる、という、不当な立場に置かれます。つまり、加害側に寄与し、被害側に著しい不利益を生じさせます。
これが世界規模で起きたら、武力によって他国を侵略する側に多大な利益を、侵略される側に多大な不利益を与えます。
つまり、こういう戦いまで、表面だけを見て「喧嘩両成敗」という思考を発動させるのは、それがどんな戦いなのか内実を見ようとしない、思考停止という名の思考です。
これは上述の「知的」に見える「分析」も同様です。事態を客観的にとらえているようでいながら、「両者それぞれに、相応の言い分がある」、つまり「喧嘩両成敗」という思考をベースにしており、両者の対立による戦争と、侵略戦争とを区別することをしていないのです。知識はあっても、その分析が、どのような事態を引き起こすかまで想像していないという点、浅慮だと思いますし、思考停止と言っていいのではないかと思うのです。
私はこの思考停止思考が、非常に厄介な戦争想念であることに思い至りました。
これまで述べてきたように、侵略者は世界を征服するまで侵略をやめません。可能な限りそれを成し遂げようとします。侵略者に利すれば、それはすなわちさらなる侵略に加勢することになります。戦争は拡大するでしょう。それが終わるのは、世界が独裁者に支配され、独裁者に都合のよい「秩序」ができたときでしょう。世界は闇の手に落ちるのです。
つまりこの、一見すると平和主義の、思考停止思考は、戦争に寄与する戦争想念なのです。厄介なのは、そもそも戦争想念に見えないこと、そして、誰もが陥りやすい心理状態であることです。
今回は、戦争想念、そして戦争想念に見えない戦争想念について見てきました。次回は、戦争を引き起こす独裁者について、もう少し掘り下げてみたいと思います。